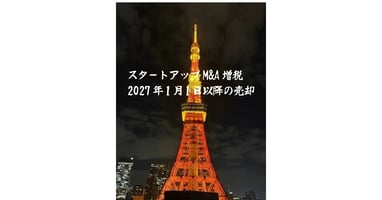M&A(企業の合併・買収)を行う際、税金は必ず考慮すべき重要な要素です。買い手側、売り手側の双方にさまざまな税金が課され、その総額は取引規模や内容によって大きく異なります。
本記事では、M&Aに関する税金の総額がどの程度かかるのか、具体的な計算例を交えてわかりやすく解説します。あくまで一般論を整理しているだけなので、実際の税金については、必ず税理士・会計士などの税務専門家に具体的に相談することを推奨します。
M&Aの税金は総額いくらかかるのか?
M&Aでかかる税金は、売却側と買収側の立場や取引形式(株式譲渡・事業譲渡)によって異なります。以下に、それぞれのケースを解説します。
売却側にかかる税金
株式譲渡の場合
売却側の譲渡益(株式の売却価格 − 取得価格)に対して課税されます。
税率は以下の通りです。
個人の場合:
- 所得税:15%→22.5%(ミニマムタックス対象の場合)
- 復興特別所得税:0.315%
- 住民税:5%
- 合計税率:20.315%、約20%→約27.5%(ミニマムタックス対象の場合)
(参考)2025年1月1日以降のミニマムタックスの概要:
- 対象者:年間合計所得が3.3億円を超える超富裕層。
- 税率:3.3億円を超える部分の所得に対して22.5%の税率が適用
- 計算方法:(合計所得金額 - 3.3億円) × 22.5% - 通常の所得税額 = 追加納税額
法人の場合:
例)株式売却益が1億円の場合、個人なら他の所得次第で約20百万円〜27.5百万円、法人なら約29百万円〜42百万円の税金がかかります。
事業譲渡の場合
法人による事業譲渡において、譲渡資産(設備、在庫、不動産など)の利益に対して課税されます。
事業譲渡では以下の税金が発生します。
- 法人税: 利益に基づく課税(29~42%)
- 消費税: 課税資産に応じて10%
事業譲渡で得た利益(売却価格-帳簿価額)が法人の課税所得となり、法人税(総合課税方式で29~42%の法人税率)が課されます。また、譲渡対象が課税資産(商品、設備など)の場合、消費税の課税対象となります。
例)1億円の譲渡益が発生した場合、約29百万円〜42百万円の法人税と、譲渡対象資産による消費税(最大10百万円)がかかります。
買収側にかかる税金
株式譲渡の場合
株式譲渡では、通常買収側に税金は発生しません。ただし、登記費用や契約書作成に伴う印紙税がかかります。
事業譲渡の場合
- 消費税: 課税対象資産(設備、在庫など)に対して10%。
- 登録免許税: 不動産が含まれる場合は、移転登記に評価額の1.5%~2.0%が課税されます。
例)不動産評価額が1億円の場合、登録免許税は200万円。資産譲渡に伴う消費税が500万円発生する場合もあります。
総額のシミュレーション
取引金額や内容に応じて税金総額は異なりますが、以下は1億円のM&A取引のモデルケースです。(他の所得がある場合と無い場合で異なる。)
株式譲渡(個人売却の場合)
- 売却側:譲渡益に対する所得税等 →約20百万円〜27.5百万円
- 買収側:印紙税 → 6万円(契約額1億円の場合)
合計税額:約2,037万円
事業譲渡(法人による事業売却の場合)
- 売却側:法人税 → 約29百万円〜42百万円
- 買収側:消費税 → 10百万円(課税資産1億円の場合)
- 登録免許税 → 200万円(不動産評価額1億円の場合)
合計税額:約39百万円〜52百万円
注意点
- 譲渡価額が時価より著しく低い場合、売手の法人は譲渡価額と時価の差額が寄付金とみなされ、損金不算入の取り扱いを受ける可能性があります。
- 譲渡価額が時価より著しく高い場合、買手の法人は受贈益として法人税の課税対象となる可能性があります。
M&Aで課税対象となる税金の種類
M&Aにおいては、さまざまな税金が課税されるため、事前にその種類を理解しておくことが重要です。
これらの税金を正確に把握し、適切な対策を講じることで、M&Aの成功に向けた重要な一歩となるでしょう。
法人税
法人税は、企業が得た利益に対して課される税金であり、M&Aの取引においてもその影響は避けられません。特に、売却側の企業が譲渡益を得た場合、その利益に対して法人税が課税されることになります。
法人税の税率は国や地域によって異なりますが、日本の場合、一般的な法人税率は約23.2%です。ただし、中小企業には軽減税率が適用されることもあり、これにより税負担が軽減される場合があります。日本の法人実効税率は、企業の規模や所在地などの条件によって異なりますが、標準税率としては 29.74% とされています。
法人実効税率の内訳:
法人税:23.2%
地方法人税:2.3%
法人住民税:3.7%
事業税:3.6%
特別法人事業税:0.9%
これらを合算すると、29.74% となります。
注意点:
中小企業の軽減税率:資本金1億円以下の中小法人の場合、年間所得800万円以下の部分に対しては、15%の軽減税率が適用されます。
地方税の変動:法人住民税や事業税は、各自治体の税率によって異なるため、所在地によって実効税率が変動する可能性があります。
したがって、具体的な法人実効税率は、各企業の状況や所在地によって異なることを考慮する必要があります。
M&Aの際には、譲渡益の計算が重要であり、適切な評価を行うことが求められます。
また、法人税の計算においては、譲渡資産の簿価や譲渡価格、関連する費用などを考慮する必要があります。これにより、実際に課税される利益が変動するため、事前にしっかりとしたシミュレーションを行いましょう。
さらに、法人税の申告期限や納付期限を守ることも重要で、これを怠ると延滞税が発生する可能性があります。
M&Aを検討する際には、法人税の影響を十分に理解し、適切な対策を講じることが、税負担を軽減するための鍵です。
個人所得税
M&Aにおいて、売り手が個人の場合、個人所得税が課税されることになります。個人所得税は、売却によって得られた利益に対して課される税金であり、具体的には譲渡所得として扱われます。
譲渡所得は、売却価格から取得費用や譲渡にかかった費用を差し引いた金額で計算されます。譲渡所得に対する税率は、所得税と住民税を合わせた累進課税制度に基づいており、所得が高くなるほど税率も向上。
具体的には、所得税は5%から45%の範囲で、住民税は一律10%です。これにより、M&Aによる売却益が大きい場合、税負担も相応に増加することになります。
また、個人がM&Aを通じて得た利益が特定の条件を満たす場合、特別控除が適用されることもあります。たとえば、一定の保有期間を経た株式の譲渡に対しては、特別控除が適用されることがあり、これにより税負担を軽減することが可能です。
消費税
消費税は商品の販売やサービスの提供に対して課税されるものであり、M&Aにおいてもその適用が考慮されます。
具体的には、事業譲渡の場合、譲渡される資産が消費税の課税対象となることがあります。これにより、売り手側は譲渡価格に消費税を上乗せして請求することが可能です。
一方、株式譲渡の場合は、消費税は課税されません。これは、株式そのものが資産の譲渡ではなく、企業の所有権の移転と見なされるためです。このため、M&Aの形式によって消費税の取り扱いが大きく異なることを理解しておくことが重要です。
また、消費税の課税対象となる場合、売り手側は消費税を適切に計算し、納税義務を果たす必要があります。
登録免許税
登録免許税は、企業の合併や買収に伴い、登記手続きを行う際に発生します。具体的には、会社の商号や本店所在地の変更、株式の譲渡、事業譲渡に関連する登記などが該当します。
登録免許税の額は、取引の内容や規模によって異なりますが、一般的には取引価格の一定割合が課税されます。例えば、株式譲渡の場合、譲渡価格に基づいて計算されることが多く、事業譲渡の場合も同様です。
具体的な税率は、各都道府県によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、登録免許税は一度の取引に対して発生するため、M&Aの規模が大きいほど、その税額も増加します。したがって、M&Aを検討する際には、登録免許税を含めた総コストをしっかりと把握し、計画的に進めることが求められます。
住民税
住民税は、個人や法人が居住する地域の自治体に納める税金であり、所得に基づいて課税されます。具体的には、法人の場合は法人住民税、個人の場合は個人住民税としてそれぞれ異なる計算方法です。
法人住民税は、法人の所得に対して課税されるもので、都道府県民税と市町村民税の2つに分かれています。これらは、法人の所得に応じて一定の税率が適用され、M&Aによって得られた利益もこの課税対象に含まれます。
特に、事業譲渡の場合、譲渡益が法人の所得として計上されるため、住民税の負担が増加する可能性があるのです。
一方、個人住民税は、個人の所得に基づいて課税されるもので、給与所得や事業所得、譲渡所得などが対象となります。M&Aにおいて、売り手が個人事業主である場合、譲渡益が個人の所得として計上され、住民税が課税されることになります。
このため、売却時の所得状況や譲渡価格によって、住民税の額は大きく変動することがあります。
住民税は、M&Aの結果として得られる利益に対しても影響を及ぼすため、事前に税金の計算を行い、適切な対策を講じることが重要です。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物、設備などの不動産に対して課される税金であり、企業が保有する資産の価値に基づいて計算されます。M&Aの際には、買い手側が取得する資産に対してこの税金が発生するため、取引の総コストに影響を与える要因です。
具体的には、固定資産税は毎年課税されるため、M&A後も継続的に支払いが必要です。特に、譲渡される不動産の評価額が高い場合、固定資産税の負担も大きくなります。
したがって、M&Aを検討する際には、対象となる固定資産の評価額や、過去の固定資産税の支払い状況を確認することが重要です。
買い手側と売り手側のM&Aの税金の違い
M&Aにおいて、買い手側と売り手側では課される税金の種類やその負担が異なります。
売り手側は、譲渡益に対して法人税や個人所得税が課税されることが一般的です。特に、売却によって得られた利益は、法人の場合は法人税、個人事業主の場合は個人所得税として課税されるため、売却価格が高ければ高いほど、税負担も大きくなります。
一方、買い手側は、取得した資産に対して消費税や登録免許税が発生します。特に、事業譲渡の場合、譲渡対象となる資産に対して消費税が課税されるため、買い手側はこの点を考慮しましょう。
また、株式譲渡の場合は、株式の取得に伴う登録免許税が発生することもあります。
さらに、買い手側は、取得した資産の減価償却を通じて、将来的に税金を軽減することが可能です。これに対し、売り手側は、譲渡益に対する課税が即時に発生するため、税金の負担が一時的に重くなる傾向があります。
株式譲渡と事業譲渡におけるM&Aの税金の違い
M&Aにおいて、株式譲渡と事業譲渡は異なる取引形態であり、それぞれにかかる税金も異なります。
まず、株式譲渡では、売り手が保有する株式を買い手に譲渡する形です。この場合、売り手は譲渡益に対して課税される法人税や個人所得税が発生します。
特に、個人が株式を譲渡した場合、譲渡益に対して約20%~27.5%の税率が適用されるため、税負担が大きくなることがあります。
一方、事業譲渡では、企業の資産や負債を直接譲渡する形です。この場合、譲渡対象となる資産に対して消費税や法人税が課税されることが一般的です。
特に、事業譲渡では、譲渡した資産の評価額に基づいて税金が計算されるため、譲渡価格の設定が重要なポイントとなります。
さらに、事業譲渡の場合、譲渡した資産に対して固定資産税や登録免許税も考慮する必要があります。これに対して、株式譲渡では、これらの税金は直接的には関与しないため、税金の種類や計算方法が異なるのです。
個人事業主と法人におけるM&Aの税金の違い
M&Aにおける税金は、取引の形態や主体によって大きく異なります。特に、個人事業主と法人では、課税の仕組みや税率が異なるため、注意が必要です。
まず、個人事業主が事業を譲渡する場合、譲渡益に対して個人所得税が課されます。この場合、譲渡益は事業の資産や負債の評価額に基づいて計算され、税率は累進課税です。
所得が多いほど高い税率が適用されます。
一方、法人がM&Aを行う場合、譲渡益に対して法人税が課されます。法人税は、法人の所得に対して一律の税率が適用されるため、個人事業主に比べて税負担が安定しているといえます。
また、法人の場合、事業譲渡と株式譲渡の選択肢があり、それぞれに異なる税務上の影響があります。特に、株式譲渡の場合、譲渡益に対して法人税が課されるため、税務戦略を考慮することが重要です。
さらに、個人事業主は事業の譲渡に際して、消費税や住民税、固定資産税なども考慮する必要がありますが、法人の場合はこれらの税金が異なる扱いを受けることがあります。
M&Aを通じて会社を売却する際には、税金の負担を軽減するためのさまざまな節税対策を講じることが重要です。対策を駆使することで、M&Aに伴う税金の負担を軽減し、より有利な条件での取引を実現することができます。
M&Aに関連する税金については、多くの疑問が寄せられます。特に、税金の優遇措置や節税対策、誰が税金を負担するのかといった点は、買い手側と売り手側の双方にとって重要な情報です。これらの質問に対する明確な回答を知ることで、M&Aを行う際の不安を軽減し、より良い意思決定を行う手助けとなるでしょう。
M&Aにおける税金は、取引の種類や規模によって大きく異なるため、事前にしっかりとした理解が必要です。法人税や個人所得税、消費税など、さまざまな税金が課されることを考慮し、買い手側と売り手側の立場での違いも把握しておくことが重要です。
また、株式譲渡と事業譲渡の選択によっても税金の負担が変わるため、慎重な判断が求められます。
さらに、個人事業主と法人では税金の取り扱いが異なるため、自身の状況に応じた適切な対策を講じることが必要です。節税対策としては、売却形式の選定や売却価格の調整、特定の税制優遇措置の活用などが考えられます。
M&Aを成功させるためには、税金に関する知識を深め、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。